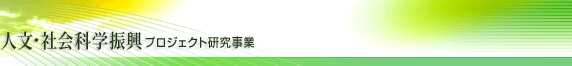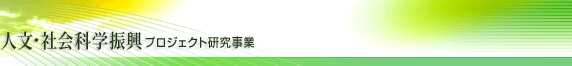公開シンポジウムでは、日本の「知」の継承と創造について、
「何を・誰が・どのように」という視点から検討が行われました   パネルセッション1 学校教育と企業内人材育成の連携を探る 
パネルセッション2 市民という担い手をつくる
パネルセッション3 社会における教育の役割を考える
・パネルセッション1(11.00-11.50)
「学校教育と企業内人材育成の連携を探る」
報告者 葛西康徳(新潟大学大学院実務法学研究科・教授)
加登 豊(神戸大学大学院経営学研究科・教授)
コメンテイター 洪政国氏(日本IBM株式会社)
  
加登さん:
「優れた人材を育てれば企業はよくなる と人事の人は考えているが、優れた人材をあつめるだけではだめだ。当然優勝しなければならないチームが4位5位に甘んじていることを見てもわかる」
岡田「協働力を高めないと個人の実力も発揮できないのではないか」
洪さん:「韓国の人は日本へ勉強に行かない。1番のアメリカへゆく。
しかし日本にあって韓国にないものは『老舗』。「継ぐ」という精神は韓国にはない。老舗を守ると言うのは上昇志向はないと思われる。」
岡田「上方の「継承」文化を再生させなければという思いがしました」
・パネルセッション2(12.00-13.00)
「市民という担い手をつくる」
報告者 佐藤 学(東京大学大学院教育学研究科長)
村松 伸(東京大学生産技術研究所・助教授)
コメンテイター 小長谷有紀(国立民族学博物館・教授)
  
佐藤さん:
「教科書を調べてみると例えば社会を成り立たしめている「貨幣」について学校では習っていない。現代社会は心と心がつながって成り立っているのではない。」
村松さん:小学校での実践教育のビデオがすばらしかったです
「前の人々から受け継いだものを減らさず損なわずに、よいものを付け加えて次に伝えたい」
小長谷さん:
「教育の分野はプロじゃない人もみな一家言持っている分野。」
「佐藤先生、アリストテレスを持ち出さないで、市民性ということばを使わないで教えるひとと教えられる人の関係性を変えてゆくメニューを作ってみてくださいな」
<昼食>
・パネルセッション3(14.00-14.50) 総論パネルセッション
「社会における教育の機能分担」
報告者 苅谷剛彦(東京大学大学院教育学研究科・教授)
木村武史(筑波大学大学院人文社会科学研究科・助教授)
コメンテイター サトウタツヤ(立命館大学大学院文学研究科・助教授)
 
苅谷さん「教育の地殻変動と「学習資本主義社会」のゆくえ」
「先生を養うために、教育の質と関係なく教育人件費は上がる。=地殻変動
学歴社会から学習資本主義へ転換する時代です。
「教育」を「学習」と呼び変えただけではだめです」
・テーブルセッション

「何を・誰が・どのように」という視点についてテーブルを分けて討論し、
社会提言すべき内容を検討しました。
    
「だれが」チーム(コーディネータ萩原なつ子氏)の第2テーブルのみなさん

  
問題が多様であることが指摘され、こんなに問題がある、ということが、様々な形で明らかにされました。
つぎは、いつも思うことなのですが、他人に(あるいは他の立場の人に)ああすべきだ、こうすべきだと言うだけではなく、「わたしは何をするのか」と一人称で考えることをしなければ。
そのときは、これはだめ、あれもだめとだめだと思うことをならべることに精力を使ってしまうともう実際に知を継承するという行動を起こす力がなくなってしまいます。
・こんな教育がよかった
・こんな学習がよかった
・こんな知に感動した、助けられた
といううまい話(延藤班の平川さんグループがおっしゃったgood practice)もうまく集めてうまく伝達してゆく工夫をしてみたいものです。
システム論はじーんと心のそこに響く実践例の中から生まれると思います。
これを競う「教育出る杭」「学校の日ワークショップ」はいかがでしょう?  石井紫郎先生 石井紫郎先生 学術振興会鈴木さま 学術振興会鈴木さま
|