葉山ハートセンター集合 須磨久善先生のご説明で手術の模様を拝見する
【パワーポイントで導入】
■血管は緩んだり縮んだりする これを緩ませる注射をする[血管は生きている]

■5000年の歴史の或る外科手術の中で心臓手術の歴史は50年。
1950アメリカのジョンギボン開発の人工心肺の発明によって可能になった
■手術者が心がけること
・体調に気を使う。 運動や食事にも配慮
・気持ちの切り替えが大切
■患者さんとのコミュニケーション
・話をよく聞いて、背中をさすって、安心してもらう。
信頼関係を作って手術を行うのとそうでないのとでは長い目で見たところ違ってくる
■病院空間とコミュニケーションとの関係
・ゆったりした気分で仕事をすることが大切。そこでよいコミュニケーションができる
・働いている職員がまず気持ちいいと感じる空間にすることが、よいコミュニケーションを生む
そのため病院内の設計では様々な工夫がなされている
・部屋を広く取った 通路もたっぷり
・部屋の壁面全部収納庫、
・病院内アメリカ松とクリームイエローの壁
・壁と床との境目は直角でなくR(ゴミがたまらない)
・線が床を這わないように
■外科医と心臓とのコミュニケーション
・どれだけの時間で手術をしたか、その時間がその心臓にとってふさわしいかどうかが大切
・弱っている心臓ほど手術しなければならない。短い時間内で施術しなければならない
・開けた瞬間に心臓と会話することもある。
・リスクの高いときのほうが多い。

■手術室での会話
・公開手術では大画面を見ている専門家たちから質問が来る。それに答ながら手術するのは大変。しかしうまくいくとその手術法が広まるので、大切なことではある。
・にぎやかな医師と静かな医師がある。須磨先生は物静かなほう
■医療者間のコミュニケーションと信頼関係
・自分で手術ができるようになったら自分で自分の手術をしたいか?ーしたくない。
・医療は人と人との係わり合い 人を相手にする仕事とものを相手にする仕事と仕事には2種類
医療は人を相手にする仕事のさいたるもの。人を信頼することを大切にしないと遣ってゆけない職業
医療従事者に向いている人はある。もの相手が向いている人が医師になっても幸せになれない
■ 外科医の資質として要求されるのは?
・責任感 人の身体に傷をつけて感謝されるのは外科医だけ。その行いに責任をもつ
・判断力 想定外のことが起こったときに どのオプションを選択するかを迅速にする必要がある。教育ではだめ
■本物を示すために子どもたちに手術を見せる ・これまで3000人ぐらいが参観した
・こどもたちと会うようになって安心した。子どもたちが感性がなくなったということはないとよく分かった

■日本と海外の違い
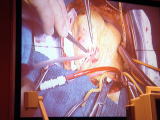
・心臓外科の現状 日本では40,000人/年間 手術を受ける。
病院が多すぎて、ひとつの病院で週に2例ぐらいしか手術をしていない。
技術を磨くには少なすぎる。quality controlが海外ではきちんとされている。
■これからは?
・この病院をつくったのは「居心地のいい病院というのはこんなものだ」というものを形にして見せたかった
・葉山ハートセンターをつくって5年、外科医としてやりたいことはある程度できた。
・4月から研究のため、六本木の財団法人 心臓血管研究所に移った
■
 子どもたちの血圧を測る鈴木看護師 子どもたちの血圧を測る鈴木看護師
(千代さんと岡田の会話)手術中は医者たち看護師が一体。チーム医療というのはこの一体感から生まれる。
これが患者とのコミュニケーションにも反映する

【引き続き須磨先生のお部屋でお話をうかがう】
■自分が分かっていることを他人にいかにわかりやすく伝えるか
医の現場での伝達は きちんと伝えるということを目指す サプライズであってはならない
そのためにはまず自分が分かっていないといけない
□どういうものなのか
□なぜそれを行う必要があるのか
□ひとりずつの役割はなにか(何をやるのか やってはいけないのか)
□責任は自分が取るから安心してやりなさい
を明確にチームに示す必要がある。
創造的な仕事に手を染めるときには、ひとりでこれらがイメージできて言えなければならない。
■確認の重要性
相手が正しく理解してくれたかどうか確認する
リラックスさせておいて 分かっているかどうか確かめる
別の言い方で語ってみる。理解していたら応えられるはずだという質問をする
■自由と責任は両立する
責任を明確にしてそれを果たすことによって自由になる 信頼関係も成り立つ
責任を果たせていないと縛られる
己を知ることがコミュニケーションの必須要件
◇まず自分はなにをしたら幸せなのかを知る 「自分が幸せでないと他人を幸せにすることはできない」(須磨先生)
◇そのために何をしたらよいかを知る
◇なぜそれをするのか、それはどういうものなのかを正しく知ってまわりにきちんと伝える
◇責任を明確にしてそれを果たす。フィードバックをもらう。
◇自由になって自ら変化する。ひとつのポーズに固執しない
研究室経営にとっても、須磨先生のコミュニケーション論や責任論は大変参考になることが多かったです
濱町さんは自らも助産師という医療関係者であるので、手術のわざに大きな感銘を受けられていました
建築がご専門の千代さんはさまざまな病院空間とコミュニケーションに関する質問をしてくださいましたが
眼に不思議な光を宿して「30年早かったら自分は医者になった」との感想をもらされました。
プロセス研究をしている百武さんはコミュニケーションのフィードバックに関してよい質問をしてくださいました 9月発行の『感性哲学5』で先生とのやり取りを発表します(感性哲学部会編集委員会 岡田真美子)

|





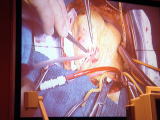
 子どもたちの血圧を測る鈴木看護師
子どもたちの血圧を測る鈴木看護師

