|
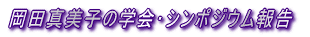
日本宗教学会第65回学術大会
公開シンポジウム 「死者と生者の接点」


| <開催日> |
9月17日(土)14.40-17.40 |
|
<開催場所>
|
東北大学法学部第1番教室 |
| <パネリスト> |
宮家 準先生(慶應義塾大学名誉教授) |
|
藤井正雄先生(大正大学名誉教授) |
|
山形孝夫先生(宮城学院女子大学名誉教授) |
| <コーディネータ> |
華園聡麿(東北大学名誉教授) |
宮家準先生 |
「以前は死者のために行われた葬送が、今日では、
残された人たちが、死者の仕事を継ぐという決意を
明らかにする式と変ってきた。
これからは一人だけ残された人の霊魂をどうしてゆくかを
ことを考えていかなければならない」 |
 |
藤井正雄先生 |
「生死については日本の文化の中で考えなければならない。
かつてはコミュニケーションの可能なものが生者、
不可能なものが死者であった。
ICTによってその区別は薄れてきている。
生者と死者の移行の場も今日忘れられている。」 |
 |
山形孝夫先生 |
かつてナイル川の西岸は人がすまなかった。そこは墓場(死者の墓)だった。西岸に修道院がある。西に住むものは死者であって、修道院は無縁の場である。修道士たちは生者の町、ナイル川東岸から死者の町西岸へ移ったことになる。生きながらに死者になった彼ら出家にとってもはや墓は必要ない。
しかし修道院に墓がある。そこにはホスティア(殉教者)のからだが祀られている。その身体は実はパン。朝それを食べるのがこのコプト教修道院の唯一の儀礼であった。
|
 |
涅槃とは、死後 「我」が滅するということを完全に納得することをいうのか、等つらつら考えた。
(岡田真美子)
研究教育 
2006年09月16日 20:07:16 更新
|



