 いよいよ6月から、身近な地域での場づくりと活動を応援する「県民交流広場事業」の募集がスタート地域の最前線で、広場の活用やコミュニティづくりを助言・支援する「コミュニティ応援隊」(CAT)が、地域の実践家や専門家の参画を得て発足しました。
いよいよ6月から、身近な地域での場づくりと活動を応援する「県民交流広場事業」の募集がスタート地域の最前線で、広場の活用やコミュニティづくりを助言・支援する「コミュニティ応援隊」(CAT)が、地域の実践家や専門家の参画を得て発足しました。| 岡田真美子の県だより | <2006年7月7日(金) ラッセホール |
| 「県民交流広場」&「コミュニティ応援隊」キックオフフォーラム |
 いよいよ6月から、身近な地域での場づくりと活動を応援する「県民交流広場事業」の募集がスタート地域の最前線で、広場の活用やコミュニティづくりを助言・支援する「コミュニティ応援隊」(CAT)が、地域の実践家や専門家の参画を得て発足しました。
いよいよ6月から、身近な地域での場づくりと活動を応援する「県民交流広場事業」の募集がスタート地域の最前線で、広場の活用やコミュニティづくりを助言・支援する「コミュニティ応援隊」(CAT)が、地域の実践家や専門家の参画を得て発足しました。
そこで、コミュニティ応援隊のメンバーが一堂に会し、これまでの県民交流広場モデル事業の実践を振り返りながら、県民交流広場をいかにしてコミュニティの再生に結びつけるのか、地域の合意と気運をいかに高めていくか、コミュニティを支える人材をいかに育てていくか、等々コミュニティを巡る課題を、会場からの意見も求めながらオープンに議論し、今後の方向性を探りました。
*CAT=Community Assist Team




と き 平成18年7月7日(金)
ところ ラッセホール TEL078-291-1117
主 催 兵庫県
共 催 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所
特定非営利活動法人はりまスマートスクールプロジェクト

<第1部> 15:00~17:30/2F「ブランシュローズ」
■オープニング・メッセージ
井戸敏三 兵庫県知事
「この県民交流広場が気楽にストレスをためず人々がかかわりあう場となって 地域活動の拠点となりますように。
CATはその名の通り、地域をひっかきまわしてください」

鳥越 皓之 県民生活審議会会長・早稲田大学教授
「世界中でコミュニティが大切な意味をもつという流れが生まれている。新自由主義のなか、行政にべったり、全員がイエスマンになるのではなく、自分の目を持って地域にかかわってゆくことがますます必要。」
■CATトークセッション
(県民交流広場とモデル実践報告)
1.これまでの歩みと検証:兵庫県県民政策部県民文化局長 山本亮三さん
「コミュニティの再生強化をめざし、人的資源の活用を応援する」
パワポ「県民交流広場 これまでの歩みと本格展開」「県民交流広場の紹介ビデオ」(14分)がわかりやすくて、とてもよかったです。
・モデル地域レポート①:南あわじ市阿万地区
江本賢司さん(阿万ふれあい交流広場推進委員会)
まだ活動が浸透したとはいえないかもしれないが、
かかわった人には着実に変化が現れている
・モデル地域レポート②:芦屋市西倉地区
細谷豊司さん(西倉地区集会所運営協議会会長)
成果として、売り上げが伸びている!
社会規範を高めていくことを目指している。
・広場検証ワークショップレポート
西 修さん 神戸まちづくりワークショップ研究会代表世話人
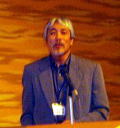
(コメントと論点提起)山下先生のコメントはすごく共感できた。本音の貴重な意見だ。
・山下 淳 同志社大学政策学部教授
「みんなで、というのは無理になっているのではないか。合意形成も難しい」
むしろ、まずは志を同じくするもののグループの中で仲良く進めて行くのでよいではないか問題は、それを回りにどうわかりやすく説明をして納得してもらうか[アカウンタビリティ]、
どうやってちゃんとやっているということを示すことができるか、である。
[いきなりグループ内にいろいろな立場のものを入れて合意形成しようとするのではなく]
ディスクロージャーとアカウンタビリティを発揮して気の合うグループ内と外との間に、
合意を形成することをめざしてはいかが。■仲良しグループでは運動の展開、発展性がないではないか---
「自分たちがまずやる、それにユーザがいる、という考え方はどうだろう。
そのユーザがつぎにプロバイダになれば、新しい展開もうまれてくるではないか。」
■行政はどうするのか---
「なにを持っているかを確かめて、それをどう手放すかが大切。スキルも含めて。」
■県と市町の棲み分けはどうなるか---
「県と市町は、仕事をどちらがするか、ではなく、どういっしょにするかである。」
■コミュニティってなに?---
「コミュニティというひとつの塊があると考えるのではなく、色んな自由にやれるグループをたばねたものをコミュニティだと考えてはどうだろう」
やれるところから、やれるものが手を付ける、というゲリラ的地域づくりに理論的なバックアップをいただけました!
★やりたいことをやりたいものたちがやる。それをまわりのひとに、いいもんだな、とわかってもらう。
↓周りの人がユーザになる
↓次にユーザの中にも、なにかやりたいことが出てくる。
★それをやりたい人たちがやる(=ユーザがプロバイダになる)
(フリートーキング)
・CATメンバー間、CAT・会場参加者間で実施
辻信一さん(まちづくりワークショップ研究会) 小橋さん(丹波 地域間の交流もできたらいいな)、


米田良一さん(養父 課題はリーダー育て。補助が終わったあとのことを考えて金をかけない活動をめざす)
橋本武司さん(たつの)
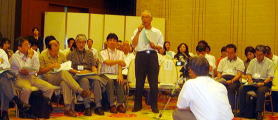

和崎宏さん(CAT HSSPすごくうまいまとめでした。ご本人からWebWeb発信されるでしょう) (尼崎)




■CAT自主プロジェクト紹介
最後に鳥越先生から、
議論は総論賛成、各論反対が常である。
ならばまず総論賛成の部分をわかりやすい3つ4つのスローガンで表してみなが賛成する場をつくる。
しかるのちに個々のユニークな活動を開始し、定期的に集っていってはどうか
というご提案がありました。つまりその<みんなに受け入れてもらえる場>が「県民交流広場」なのですね。
そして、そこからいろいろな仲良しグループが生まれ、またグループが戻ってきて交流し、合意を形成してゆく。
これが県民交流広場のビジョンとなるのかしら、と思いました。
| (c)2006 Prof. Dr. OKADA Mamiko |
<第2部> 18:00~19:30/B1F「リリー」 第2部で選ばれた交流広場キャラクターのひとつ
■交流会 *会費制(3千円、当日に受付で) 岡村果林さん制作
お問い合わせ先
〒651-1432 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県生活創造課 県民交流広場係
TEL 078-362-4004 FAX 078-362-3908
E-MAIL hiroba_seikatsusouzouka@pref.hyogo.jp
コミュニティ応援隊(CAT)〔五十音順、6月1日現在〕
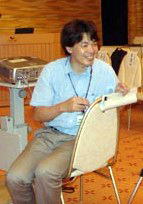
足立 宏之 丹波市神楽モデル地区 NPO法人神楽の郷理事長
岩木 啓子 ライフデザイン研究所FLAP代表
江本 賢司 南あわじ市阿万モデル地区 ふれあい交流広場推進委員会会長
奥村 和恵 多可町ベルディホール顧問
加藤 恵正 兵庫県立大学経済学部教授
桐山 法子 ㈱遊空間工房まちづくり担当
直田 春夫 (特)NPO政策研究所理事長
田中 正人 ㈱都市調査計画事務所、神戸まちづくりワークショップ研究会
辻 信一 ㈱環境緑地設計研究所取締役、(特)神戸まちづくり研究所、神戸まちづくりワークショップ研究会
東末 真紀 (特)神戸まちづくり研究所事務局
鳥越 皓之 早稲田大学人間科学学術院教授
永富 聡 (特)大阪湾沿岸域環境創造研究センター研究員
永見真利子 シンクタンク研究員
新川 達郎 同志社大学大学院総合政策科学研究科長・教授
西 修 神戸まちづくりワークショップ研究会代表世話人
野上 和雄 (特)ドラマ九鬼奔流で町おこしをする会事務局長
野崎 隆一 (特)神戸まちづくり研究所理事・事務局長
久 隆浩 近畿大学理工学部教授
細谷 豊司 芦屋市西蔵モデル地区 集会所運営協議会会長
前川 裕司 (特)コムサロン21理事長
松原 永季 (有)スタヂオ・カタリスト代表取締役、神戸まちづくりワークショップ研究会
三井津勝之 稲美町天満南モデル地区 県民交流広場推進協議会会長
森 綾子 (特)宝塚NPOセンター理事兼事務局長
森川 稔 ㈱アーバンスタディ研究所代表取締役
山崎 義人 神戸大学大学院自然科学研究科COE研究員
山下 淳 同志社大学政策学部/大学院総合政策科学研究科教授
山本 辰久 ㈱日本総合研究所研究事業本部主任研究員
米田 良一 養父市関宮モデル地区 大谷校区地域推進委員会
和崎 宏 (特)はりまスマートスクールプロジェクト理事長
☆ CATは、これまでのモデル地域リーダーや、昨年度のモデル事業検証にご尽力いただいた専門家、ファシリテーター(ワークショップの進行役)等の皆さんを中心に発足しました。他にも各分野の専門家の皆様にお申し出いただいており、順次拡充の予定です。
☆ 県民交流広場及びCATの詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
◇◆ 県民交流広場ホームページ(全県)http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/souzouka/hirobaindex.html ◆◇